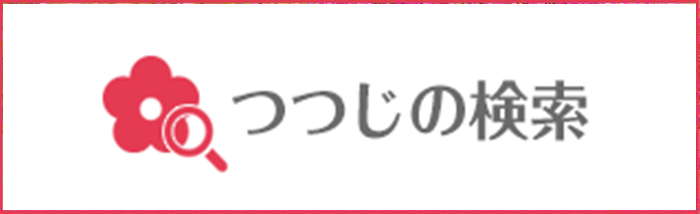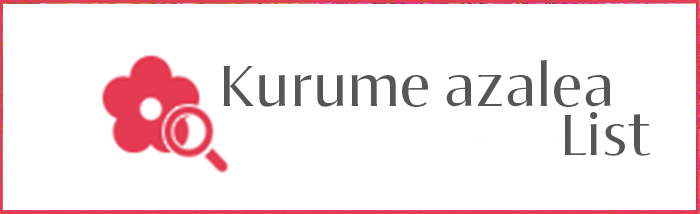久留米つつじの歴史
久留米つつじは、江戸時代の天保年間に久留米藩士の坂本元蔵(1785-1854年)が、ツツジの播種方法「苔蒔き法」を考案し、実生を人工的に育て、新品種を作ったことに始まります。幕末には品種数が200に達しました。
明治時代になると、愛好家に加え、生産業者が品種を作るようになり、500以上の新品種ができました。昭和時代になると、それまでの鉢植えから公共花木としての用途が開発され、生産量が増加しました。
このツツジグループが「久留米つつじ」という名称に一本化されたのは、1945年以降のようです。江戸時代は「小霧島」、「映山紅」と呼ばれていました。1895年には愛好家により「錦光花」という名称がつけられました。赤司廣楽園では、明治時代の終わり頃から「久留米躑躅」という名称で販売されていました。
-


- 江戸時代
-
- 1785年
- 久留米つつじ栽培の始祖とされる坂本元蔵が誕生。
- 1842年
- 久留米つつじ栽培を復興させた初代赤司喜次郎が誕生。
- 1846年
- 坂本元蔵と同好者が品種品評会を開催。
- 1849年
- 坂本元蔵と同好者が品種番付を制作。
- 1854年
- 坂本元蔵が死去。
- 幕末
- 品種数が200に達する。
-


- 明治時代
-
- 1873年
- 初代赤司喜次郎が赤司廣楽園を開園。
- 1881年
- 赤司廣楽園がツツジの銘鑑を発行。
- 1891年
- 明治維新で衰退していた久留米地域のツツジ栽培が、国内の花き園芸熱が高まるにつれて盛んとなる。
- 1895年
- 錦光花という名称で、天皇陛下へ献上。
- 1903年
- 赤司廣楽園が第5回内国勧業博覧会に出品し、二等賞となる。
- 1905年
- 赤司廣楽園が久留米躑躅誌を発行(江戸時代の久留米つつじ154品種が記載)。その後、第五版(1934年)まで発行。
- 1906年
- 東京に移った筑紫園の大石進が横浜植木と交渉し、アメリカ輸出の端緒を開く。
- 1909年
- 「誰が袖」が横浜植木のカタログ(英語版)にAZALEA INDICUM, "TAGASODE"として 、写真付きで掲載。
- 1910年
- 初代赤司喜次郎が、農林省園芸試験場谷川利善技師から人工交配技術を学ぶ。
-


- 大正時代
-
- 1912年頃
- 中野勝次郎を中心に、有力な業者を網羅した錦光会が組織される。
- 1914年
- 紀州の堂本氏がアメリカへ輸出。
- 1915年
- 赤司廣楽園がパナマ・太平洋万国博覧会に12品種を出品し、金賞を受賞。
- 1917年
- 初代赤司喜次郎が、東京帝国大学藤井健次郎教授から花粉貯蔵法を学ぶ。
- 1917年
- ドーモト・ブラザーズ・ナーセリーが、アメリカでの輸入販売の専有権を得る。
- 1918年
- アーネスト・ヘンリー・ウィルソンが赤司廣楽園で50品種を購入し(江戸キリシマ2品種を含む)、ハーバード大学付属アーノルド樹木園に導入。これらの品種はウィルソン50と呼ばれる。
- 1920年
- 初代赤司喜次郎が死去。
- 1920年
- ドーモト・ブラザーズ・ナーセリーが、25品種5000株をアメリカに輸入。
- 1920年
- ウィルソンがマサチューセッツ園芸植物展示会にウィルソン50を出展し、金賞を受賞。(このとき江戸キリシマ2品種は除かれ、「小蝶の舞」が加えられる。)
- 1920年代初め
- ウィルソンがイギリスのJ. C. WilliamsとJ. B. Stevensonにアメリカからウィルソン50を送る。
-


- 昭和時代
-
- 1927,1929年
- J. B. Stevensonが横浜植木からウィルソン50以外の80品種を購入。
- 1931年
- 浅野陽吉が躑躅考を発行。
- 1945年以降
- 名称が久留米躑躅(くるめつつじ)に統一。
- 1953年
- くるめつつじ振興会が結成。鉢植えから庭園木、公共花木として利用するための活動が始まる。
- 1957年
- 久留米市で、久留米つつじまつりが始まる。
- 1975年頃
- 花木類の重要な生産品目となる。
- 1976年
- 久留米市つつじ保存会が躑躅考(復刻版)を発行。
-


- 平成時代
- 2000年以降
- サツキとの交雑品種がクルメツツジに加えられるようになる。